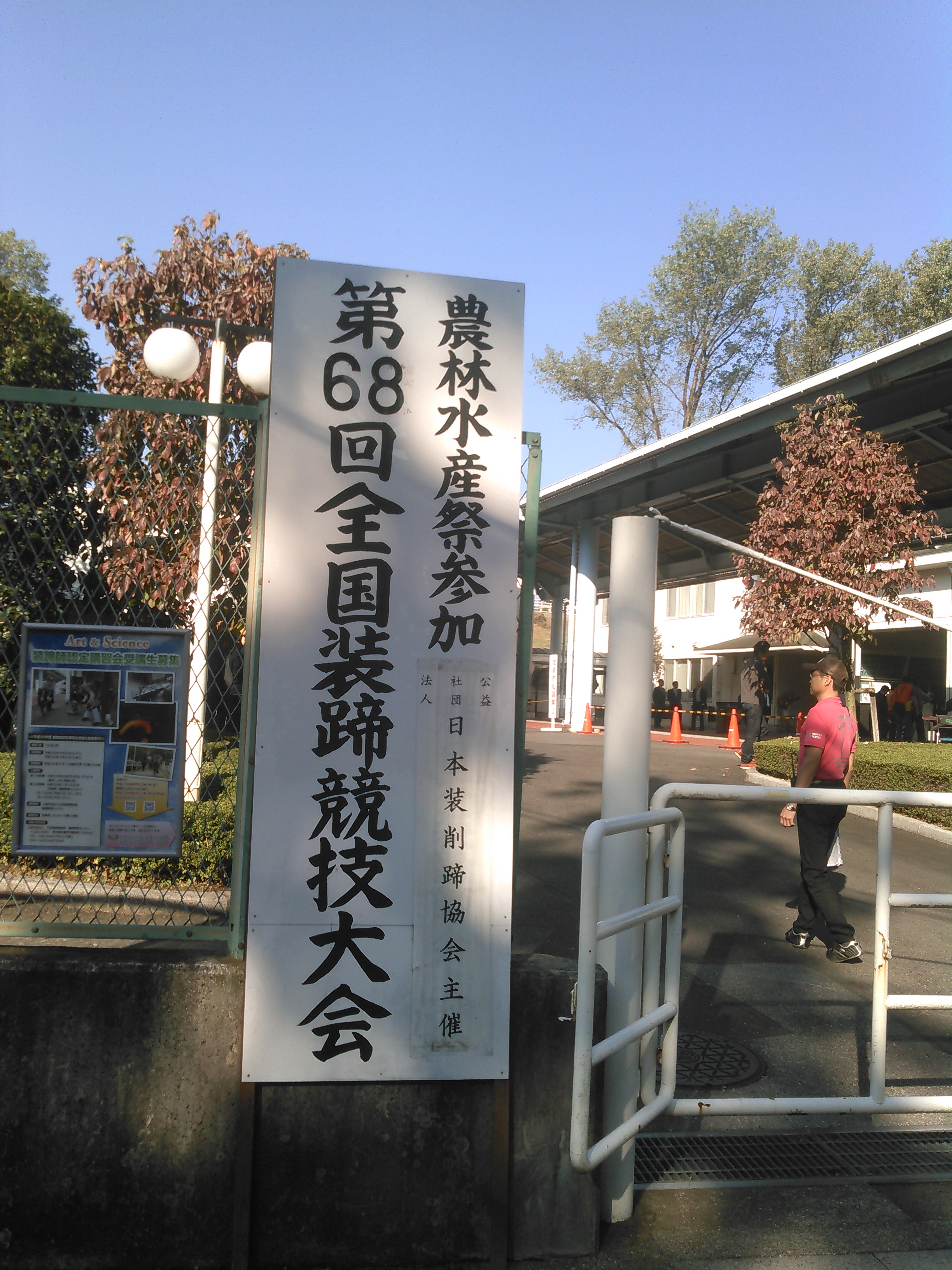これも、昔やっていたブログの温め直しのネタで恐縮なのですが、やはり、土俵がかわっても伝えたいことはそんなに変わりませんので、やらせていただきます~。
m(_ _)m
その昔立ち読みしていたら偶然この「はじまりコレクションⅠ」という本に「蹄鉄」の項目がありましてので紹介させていただきます。
むか~~し、むかし(959年)、イギリスはカンタベリーの大司教で聖ダンスタンという方がいたそうです。
実はこの大司教、聖ダンスタンさん・・・さん?? 装蹄師でした。
ある日ダンスタンのところに一人の男がやって来て自分の足に蹄鉄を付けてほしいと言ったそうな。
見ると怪しげにひづめが割れています。(悪魔はひづめが割れているようです。西洋では悪魔のモチーフは牛ですからね~。)
ダンスタンはすぐにこの男が悪魔だと見破り、蹄鉄を付けるには体を固定しなければならないと説明し、悪魔を壁に張り付けてしまったようです。
そして・・・
わざとひどく痛いやり方で・・・
蹄鉄を打ち付けました・・・。
ひぃぃぃ~~・・・ 釘のマークを外側とか? 過削とか? 過度の焼き付けとか? 鉄頭狭いとか? 鉄尾が短くて蹄踵にめりこむようにしたとか? 側鉄唇をぎゅうぎゅうにキメるとか??? いったい、どんなことしちゃったんだい!? ダンスタン!!??。
その耐え難い痛みに、張り付けられた悪魔は助けてくれるように何度も、何度もダンスタンに懇願しました。
ダンスタンは悪魔に言いました。
「今後一切ドアに蹄鉄を掛けてある家には入るなえ。」 と。
そう固く誓わせて悪魔を解き放ったそうです。
以来、キリスト教徒は蹄鉄を尊重するようになり、魔除けとしてドアに掛け、それが魔除けと同時にドアノッカーになったようです。
蹄鉄って、昔からのラッキーアイテムだったんですね~。
よく乗馬クラブの会員さんから、蹄鉄の飾る向きについてきかれるのですが、私は鉄尾が上向きになる法をおススメしております。 外国の雑誌とかではよく鉄頭が上に飾られているのをみますけど・・・ 幸運やお金が「貯まる」とかで逆さがいいと思います。
蹄鉄があるとお金がたまるかは別問題ですけど・・・ 我が家には売るほど蹄鉄がありますが・・・ 貧乏ですっ!! (ToT)
↑
これも温め直しです。なんかすいませんでした。m(_ _)m
はじまりコレクション Ⅰ いわゆる”起源”について
チャールズ・バナティー 著
日本実業出版社
1,550円(発売当時)
アマゾンのマーケットプライスででていました。